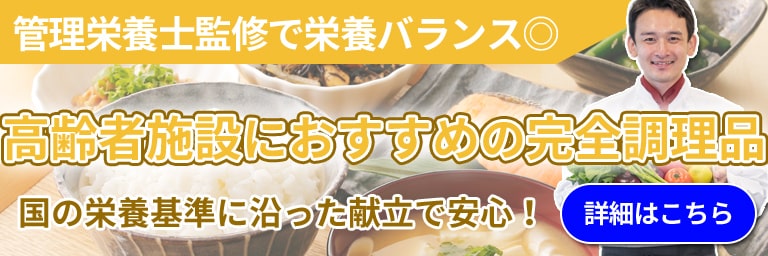糖尿病ってどんな病気?注意すべきことと日々の食事について
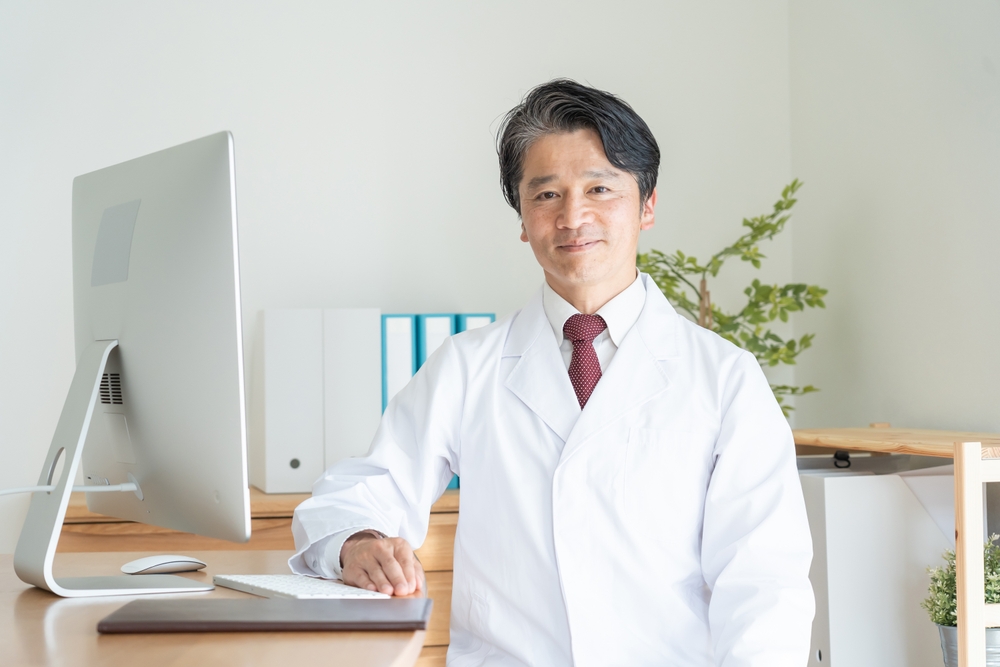
糖尿病をひとことでいえば血糖値が常に高い状態となる病気のことです。もしそのまま放置しているとさまざまな合併症が出てくる怖い病気でもあります。そうならないためにもしっかりとした治療と、生活習慣の改善が重要です。そこで今回は、糖尿病の原因や症状、治療方法、そして食事療法について解説します。
糖尿病ってどんな病気?原因や症状について
糖尿病とは、すい臓から出るインスリンというホルモンの働きがうまく作用しなくなって、血液中に必要以上に糖が増える病気です。まずは糖とインスリンがどのように体の中で働いているのかを説明しましょう。
糖とインスリン
私たちが食事をすると、栄養素の一部は糖に変化して吸収されています。糖は、血管を通って体中のあらゆる組織細胞へ届けられ、ヒトが活動するためのエネルギー源となります。
しかし、糖が体のエネルギー源として活躍するためには、インスリンの力が必要なのです。インスリンがうまく働くことで、糖が細胞に取り込まれます。糖が細胞内に入り、細胞のエネルギーとなるのです。
ところが糖を細胞内に取り込む働きがうまく作用しないと、細胞に吸収されなかった糖が血液中に残ってしまいます。その結果、血糖値が高くなり、糖尿病を発症します。
血糖値が高くなる原因
必要量の糖が細胞内に入れないのは、体内で次のようなことが起こっているからです。
・すい臓の機能が低下したために、インスリンが充分に分泌されず、必要量の糖が細胞に取り込まれなくなった状態
・インスリンは充分に作られているけれど、インスリン自体の働きが弱くなってしまい、その結果、糖が細胞内に入れない状態(インスリン抵抗性)
これらの血糖値が高くなる原因によって、糖尿病は大きく「1型糖尿病」と「2型糖尿病」に分類されます。
1型糖尿病
1型糖尿病は、すい臓のインスリン分泌がほとんどできなくなったために血糖値が高くなるタイプです。インスリンが分泌できない原因は、まだ明確にはわかっていませんが、遺伝や何らかのウイルス感染、免疫異常などが関わっていると考えられています。
インスリンがほとんど作れないため、1型糖尿病患者の方には、インスリンを補うことが生きるためには絶対に必要です。また1型糖尿病の特徴として、症状が急激に現れる場合が多いという点があります。
2型糖尿病
2型糖尿病は、
・遺伝的影響
・加齢
・食べ過ぎ
・運動不足
・肥満
・ストレス
などの環境的な要素が原因となって、インスリン分泌が低下したり、インスリンの働きが悪くなったりして血糖値が高くなったタイプです。国内の糖尿病患者のほとんどが、こちらのタイプに当てはまります。
遺伝や体質が関係して2型糖尿病となる方もいいますが、多くの場合は生活習慣が原因だと考えられています。
妊娠糖尿病ほか
妊娠中に初めて血糖値が異常に高くなった状態を妊娠糖尿病と言い、たいていの場合出産後には平常に戻ります。
ただ妊娠糖尿病を発症した方は、将来的に糖尿病の発症リスクが高くなる傾向にあるため、定期的な検診を受けておくほうがよいでしょう。
そのほかに、遺伝子異常やほかの病気に使用している薬の影響による糖尿病もあります。
糖尿病の症状
糖尿病は初期の頃にはあまり症状が出ず、病気が進行してから「糖尿病合併症」として次のようなさまざまな症状が表れることがほとんどです。
・喉が渇く
・尿の回数が増える
・疲労感がある
・皮膚の乾燥やかゆみ
・手足がチクチクする
・目がかすむ
・傷が治りにくい
・性機能の低下
これらの症状が出てくるまでに、糖尿病を発見するためには、定期的に健康診断や血液検査を受けてください。そして、少しでも血糖値以上があれば、放置せずに必ず医師にかかりましょう。
治らないってホント?糖尿病の治療法と注意点
糖尿病は、一度かかると一生治らないといわれます。確かに「1型糖尿病」は、現代では治らない病気とされています。インスリン注射は一生欠かせません。ただ近年は、再生医療による治療も行われており、いずれは完治する病気になるかもしれません。
これに対し「2型糖尿病」は、治療によって血糖値をコントロールすることで健康な人と同じような生活ができます。つまり、糖尿病とうまく付き合えば、血糖値を平常値に戻せるうえ、それを維持できるのです。
糖尿病の治療法
「1型糖尿病」の場合は、糖尿病の治療においては、日ごろの生活習慣を見直すことが重要となります。医師の指導の下、軽い有酸素運動を継続して続けることで、筋肉の量を増やし、脂肪を減らしましょう。運動療法と同時に大切なのは食事療法です。
糖尿病患者の食事管理で重視すべきポイント
食事療法とはいっても、特別なことではありません。医師の指示に従い、日々の食事習慣と摂取カロリーを見直し、実践するだけです。行うことは、ダイエットをされている方と大きな違いはないでしょう。あとは次のポイントに注意して、食事管理を行ってください。
・栄養バランスのよい食事を摂る
・1日3食をしっかりと食べる
・ゆっくりとよく噛んで食べる
・腹八分目
・野菜から食べる
・寝る前には食べない
とくにバランスのよい食事は、作るのも考えるのも大変です。毎日手作りをすることが難しいなら、手軽な調理済み食品なども活用してみるという方法もあります。
工夫をして、習慣にしていけば、これらの食事管理が当たり前の日常になっていくはずです。生活習慣で糖尿病になったのなら、生活習慣で改善しましょう。
まとめ
糖尿病は、わかった時点で少しでも早く治療を始め、生活習慣を改善することが大切です。放置さえしなければ、健康な人と変わらない生活もできます。適度な運動とバランスのとれた食事、どちらもできないことではありません。
今までの生活を見直し、しっかりと血糖コントロールをしましょう。それが、健全な新生活への道となります。あきらめずに少しずつ改善させてください。