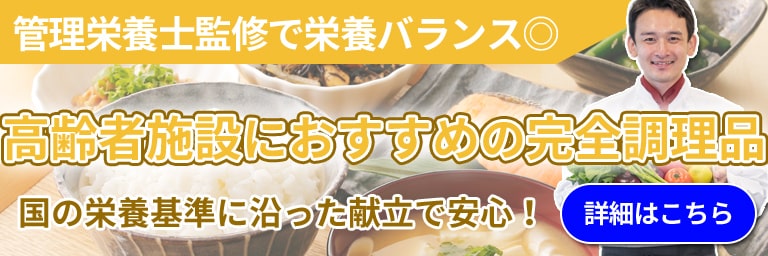意外と知らない介護報酬の話!改定したらどんな影響があるの?

高齢化社会が深刻化する日本。いまや介護についての話題は、誰しもが避けては通れない時代です。ここでは介護報酬について、その仕組みや今後の改定について紹介します。どんなサービスが利用できるかを充分に理解できている、という方はそう多くないと思います。その他、利用者が受けられるサービスについても理解を深めましょう。
CONTSNTS(目次)
介護報酬とは
介護報酬とは、介護事業者が、介護保険が適用される介護サービスを利用者に提供した場合に、その対価として受け取る費用のことです。65歳以上の被保険者が、日常生活の中での介護や支援が必要となった際、居住する自治体に要介護・要支援認定を申請して、認定されると介護保険が適用されます。
介護保険によって受けられるサービスとは、居宅介護支援や訪問看護など在宅で暮らす高齢者が受けられる居宅サービス、老人ホームにおけるリハビリや医療の提供など、入所した施設で24時間受けられる施設サービス、市町村が原則としてその地域に居住する高齢者に提供する地域密着型サービスの3つです。
日本社会の高齢化が今後さらに深刻化するという見通しから、介護報酬と介護保険の制度は2000年にスタートしました。これにともない40歳以上の国民は、国に支払う社会保険料のひとつとして、生涯にわたり介護保険料を納めることになっています。介護保険の財源は、このようにして国民から支払われた保険料と、国や自治体の公費で5割ずつ賄われています。
介護報酬の仕組みとは
介護報酬と介護保険の制度は複雑に関係しており、少々ややこしいですよね。ここでは被保険者の目線と事業者の目線に分けて、介護報酬の仕組みについて説明します。
■被保険者の負担等について
介護保険制度が施行された当初は、全員が一律1割の自己負担でしたが、現在に至るまでの改定によって、所得に応じた割合で自己負担額が変動することになりました。現在では原則1割、所得によって2割から3割の自己負担額となっています。
さらに、増加する介護保険費用における課題を踏まえ、財務省からは原則2割負担への引き上げを求める声も上がっているそうです。とはいえ介護サービスの利用により発生する費用の負担が大幅に軽減されるため、被保険者にとって非常に有用な制度であることに変わりはありません。
なお、負担割合額の基準は、世帯に65歳以上の方が何名いるかによって異なるうえ、40歳以上65歳未満の方で要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者の方、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者の方は一律1割負担です。
また、被保険者である利用者が受けることのできる介護サービスの、1か月あたりの上限単位数(区分支給限度基準額)は決まっています。そのため、利用者は残りの単位を把握したうえで必要なサービスを選択しなければなりません。この区分支給限度基準額は、要支援・要介護の度合いによって変わります。
■介護サービスの提供を行う事業者が介護報酬を受け取る仕組み
一方、介護サービスを提供する事業者はまず利用者から費用の自己負担額分を、残りの分を自治体に請求します。そして、請求額分は介護保険制度の手続に沿って処理され、窓口となった自治体から「介護給付費」として事業者に支払われる、というのが大まかな仕組みです。
事業者の提供するサービスは、その種類や内容、要介護度ごとに「単位」として法律で詳細に定められており、この「単位」に、各地域の単価をかけた額が介護報酬として支払われます。これが介護報酬の計算方法です。
各地域の単価、というのは、介護報酬の規定において設定されている地域区分によるものです。介護報酬の計算においては、地域ごとに人件費などの面で差が生じてしまうことに考慮し、日本全国を1級から7級地に振り分けた7区分と、これにその他の地域をプラスした8区分に分類し、それぞれに報酬の上乗せ割合を決定しています。
また、定められている以上の手厚いケアや人員の配置が行われた場合は介護報酬に加算され、反対に規定に満たない場合には減額されます。
介護報酬の改定の歴史と改定による影響
2000年の施行以来、介護報酬制度は、介護保険制度と共に3年ごとに改定されてきました。改定されるたびに数パーセントずつ引き上げや引き下げがなされてきましたが、2015年の改定で行われた2.27パーセントの引き下げ以降は、引き上げ傾向にあります。
直近の改定は2021年。現在運用されているのが、この2021年改定版です。たった数パーセントの変動であっても、事業主と利用者のどちらにも、報酬や負担額のダイレクトな変動につながります。
とくに、要支援・要介護認定を受けている人のほとんどが介護サービスに頼らないと生活が困難になるため、介護報酬額の変動が与える生活への影響は非常に大きいといえるでしょう。
ここまで介護報酬について紹介しました。介護報酬と介護保険の制度は、いわば両輪の関係にあり、どちらが欠けても正しく運用できなくなってしまいます。介護保険制度は非常に重要ですが、3年という短いスパンで改定されるので、常に新しい情報を手に入れられるよう、意識を向けることが重要です。
介護の分野は今後の需要増がすでに予想されているところで、介護にかかる費用から考えてみても、介護報酬の制度が社会に与える影響は計り知れません。今後介護業界の重要度はさらに増していくでしょうし、介護報酬によって介護業界で働く人への給料なども賄われることになるので、社会全体の問題として他人事と思わず向き合うことが必要でしょう。