完全調理品でも検食って必要?検食の方法と役割を改めて確認しよう

食品に関する仕事に関係していないと、なかなか馴染みのない言葉の1つに「検食」があります。検食とは高齢者施設などで行われているもので、本来の意味は「試食」と「保存」です。今回の記事では、完全調理品における検食について詳しく解説します。普段の生活では馴染みのない検食ですが、どのように運用されるのでしょうか。
CONTSNTS(目次)
検食の役割
集団で食事をする施設などを中心に行われる検食とは、そもそもどんな役割を担っているものでしょうか。
検食は厳しいルールがあり、適切な運用が求められています。ルールにされる背景には「トラブル時の原因究明」という大きな役割があります。
残念なことに、梅雨時期など細菌類が繁殖しやすい時期になると、さまざまな飲食施設で食中毒が発生しています。時には命を落としてしまうケースもあるほどです。
そこで、検食は万が一、食中毒が起きてしまった際に、その原因が一体どこにあるのかを調査するために、欠かせないものとなっています。
食のトラブルが発覚し、保健所が調査を開始した場合には、速やかに検食を提出し、調査に応じる必要があるのです。
よって、検食で保存に使われる調理済みの品々は、検食用の冷凍庫にきちんと保管を行う必要があります。安全を担保するために欠かせない行為ですので、怠らないように注意しましょう。
検食の方法は2つ
1つは、学校給食法という法律に沿って行われるものです。こちらは学校給食向けの試食を規定しているもので、子どもの食を守るためのものです。
試食としての検食は、実食し献立通りのメニューとなっているか、異臭や異物の混入は起きていないかなどを調べるために行われます。
食事提供の前に試食を終えておくことが必要です。実際にある学校給食では、子どもへの食事提供の直前に異物混入が発覚し、大勢の口に運ばれる難を逃れられたケースがあります。2つ目は保存としての意味です。
検食の保存方法
食中毒などのトラブルにも備えて、しっかりと保存しておく必要がある検食ですが、実際に保存をする際には、どんな方法が活用されているのでしょうか。
検食には、あらかじめ定められたマニュアルがあります。それは「大量調理施設衛生管理マニュアル」と呼ばれるものです。この方法は法律の1つで、検食方法や保存を厳しく定めています。
原材料と調理済みの食材を保存する
万が一の食中毒トラブルに備えて、原材料および調理済みの食材を適切に保存が必要です。検食対象の食品を50gずつ、清潔な容器に入れることが必須です。
保存する際に汚染が発生しないようにするためで、厳重に保管する必要があります。保存容器に不安がある場合には、検食専用の容器やキットを使うと便利です。
業務用に販売されています。保存後の期間にもルールがあります。マイナス20度以下で、専用の冷蔵庫にて2週間以上保存します。
なぜ2週間以上必要なのかというと、菌の中には潜伏期間が10日以上の菌も存在しているからです。使用する原材料については、洗浄や殺菌はあえて行いません。
購入時の状態のままで、保存しておく必要があります。配膳後の状態で保存し、食事をした方がどのようなものを口に運んだのかを分かるようにします。
2週間以上という長期間の保存が必要であるため、保存する検食については混乱を避けるために「〇月〇日昼食」など、分かるような表示を付けるようにしましょう。
2週間以上の経過措置が終われば、破棄ができます。しかし、破棄した日付もしっかりと管理するように注意しましょう。
食品・食事によって検食方法に差がある
では、実際の検食方法については以下です。
原材料を検食する方法とは
調理に使うためには、さまざまな種類の原材料を取り寄せる必要があります。野菜や肉類などはもちろん、加工済みの豆腐や納豆、海苔なども原材料として取り寄せることがあるでしょう。
原材料の保存は泥が付いているような素材は、あえて洗わずに食べる部分をそぐように50g保管します。食べない部分の保存は不要です。
殻がある物もそのまま保存します。肉類や魚類も同様の処理を行いますが、全て大量調理衛生マニュアル上50gという規定を順守します。
一方で、加工済みの原材料については、50gも取得すると不足に陥ることがあります。
乾燥小魚やふりかけなどが該当するでしょう。こうした加工済み原材料については、管轄保健所に保存量の判断をあおぐことがおすすめです。
調理済みを検食する方法とは
調理が完了したものも、原材料と同様に保存は欠かせません。献立通りに完成した調理済みのものについても、50g保存することが必須です。
デザートやスープなども、取り残すことなく保存します。調理が完了した段階で、一式清潔な容器に50gを保存します。
容器へ移す際には、二次汚染に注意が必要です。高齢者施設などでおやつを提供する場合には、こうしたサブメニューも、もちろん検食が必要です。たとえ完全調理品であっても、検食対象から漏らさないように注意しましょう。
まとめ
今回の記事では、検食の方法と役割について「保存」の視点から詳しく解説しました。検食は重要な作業であり、ルールを守って適切に管理を続けていく必要があります。
施設管理責任においても、いかに重要かご理解いただけたでしょうか。
日々の検食は大変な労力ですが、原材料も含めて保存をすることで、食中毒の発生時には施設側に不備はなかった、と証明できるケースもあります。大量の食事を日々提供する以上、検食は責任をもって行いましょう。


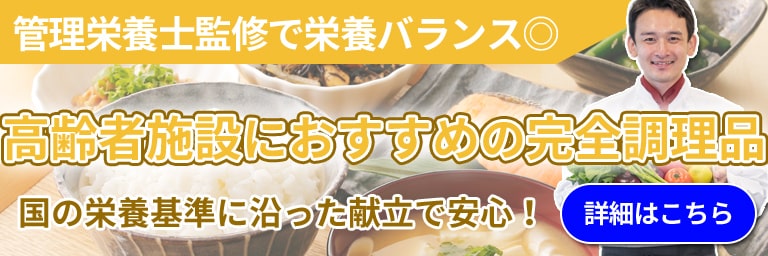






-1-150x150.png)






























